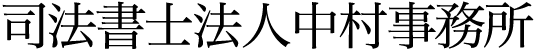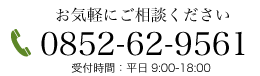相続放棄の手続
遺産分割などにより遺産を相続すると、亡くなられた方(被相続人といいます)が抱えている負の財産(借金や連帯保証債務)があれば、原則として、負債についても相続人が引き継ぐことになります。遺産分割協議によって、負債を引き受ける相続人を決定したとしても、金融機関などの債権者が負債の引き受けに同意しなければ、法定相続分に従って、各相続人が債務を負担することになります。
相続財産を確認し、負債があることが判明し、この負債を支払いたくない相続人がいる場合には、「相続放棄」の手続きを検討すべきです。
相続が開始したことを知った日(原則は死亡の日)から3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ「相続放棄申述受理申立書」を提出し、この申立てが正式に受理されると、申立人の相続人は、被相続人の財産を相続することができなくなる代わりに、被相続人の負債についても相続放棄することとなり、金融機関などの債権者の同意を得なくても支払う必要はなくなります。
上記の3ヶ月の期間を過ぎてしまっても、「相続が開始したことを知った日」(例えば、高額の借金や連帯保証債務があることが判明した日など)から3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きが可能です。
しかしながら、3ヶ月経過後の相続放棄の手続きは、3ヶ月以内の手続きのように必ず受理されるものではありません。
「相続が開始したことを知った日」について、事情を書面で上申し、家庭裁判所にこれを認めて受理していただく必要があります。
当事務所では、通常の3ヶ月以内に行う相続放棄だけでなく、3ヶ月経過後の相続放棄手続きについても実績があります。
家庭裁判所への相続放棄手続きを取り扱う国家資格者は、弁護士と司法書士のみです。
もし、負債や連帯保証債務の存在を見落として、相続放棄をしないで、遺産分割協議を行った場合には、相続した財産では支払いきれず、自分の財産で返済をしなければならなくなった事案もあります。
相続のときに、負債や連帯保証債務(事業者に多い)がある場合には、相続放棄に詳しい当事務所までお早めにご相談ください。
相続放棄の手続 ご依頼の手順
 ご予約
ご予約
当事務所まで電話またはメールフォームで、「相続放棄のご依頼(ご相談)」をご希望の旨ご連絡ください。
日程調整のうえ、面談日時を決定いたします。
持参いただきたい書類等のご案内もさせていただきます。
 面談
面談
面談日時に当事務所までお越しください。 >アクセス
事情を詳しくお伺いし、手続きについてご説明いたします。
 相続放棄に必要な書類の収集
相続放棄に必要な書類の収集
戸籍など相続放棄の申立てに必要な書類を揃えます。
 相続放棄申述受理申立書の作成・提出
相続放棄申述受理申立書の作成・提出
作成した申立て書類に、申立人の署名捺印をいただき、管轄の家庭裁判所へ提出します。
 家庭裁判所からの書面等への対応
家庭裁判所からの書面等への対応
申立書提出後、家庭裁判所からの書面照会や、審尋の呼び出しがある場合には、個別に対応をさせていただきます。
 完了
完了
相続放棄申述受理証明書を取得し、完了のご報告をさせていただきます。
相続放棄の手続 手続費用
| 司法書士報酬 |
熟慮期間内(3ヶ月以内) 1件36,000円(税別)~ 熟慮期間 (3ヶ月)経過後 1件56,000円(税別)~ |
|---|
※ 上記報酬の他、手続きに使用した収入印紙、切手、戸籍等の取得実費を申し受けます。