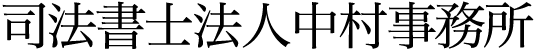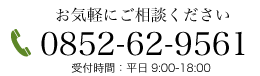遺言書の作成支援
相続が発生したとき、遺言書がある場合には、遺産については、遺言書の記載内容に従って相続承継されることになります。
遺産分割協議による遺産相続では、法定相続人全員の協議によって、遺産を誰がどの財産を相続するかを決定しますが、遺言書による遺産相続は、原則として他の相続人の同意や捺印を必要とせず、相続による取得者のみで遺産相続手続きを行うことができることが大きな違いであり、長所でもあります。
遺言書を作成しておくことは、遺された遺族が複雑な手続きを経ないでスムーズに遺産を承継することができるだけでなく、遺産分割の内容について相続人全員の合意を必要としないため、遺産分割で相続人同士で揉めてしまう可能性がある場合には、非常に有効な手段となります。
当事務所では、これまでに数多くの相続案件を取り扱って参りましたが、遺産分割の合意がまとまらず、裁判手続きによらなければ遺産分割ができないといった事案が何件もありました。
兄弟など親族同士での裁判手続きになってしまえば、どのような結果となっても、将来にわたって禍根を残すことは間違いありません。
「もし、遺言書を作っておいてくれたら、こんなに大変な思いはしなかっただろう」 遺された家族が困らないよう、特に次のようなケースに該当される方は、遺言書を作成しておかれることをおすすめします。
|
また、遺言書による遺産相続は、相続人ごとに最低限度の相続分として認められる「遺留分」を侵害している場合には、遺留分減殺請求という争いとなることもあります。
遺産を相続させたくない者がいる場合など、遺留分にも気をつけて遺言書を作成する必要があります。
遺言書の形式には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
「自筆証書遺言」は、公証役場での手続きが不要で公証人手数料の負担がないことがメリットですが、民法に定められた要件を満たしていない場合には遺言は無効となってしまうこと、相続発生後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となること、遺言書が発見されなかったり、開封・破棄されてしまう危険がある、といったデメリットもあります。
「公正証書遺言」は、公証人による作成となるため、要件不備で無効となることや、紛失のおそれもなく、また、家庭裁判所での検認手続きも不要となります。
遺言の内容を確実に執行するには、公正証書遺言の方が優れていると考えられますが、費用面や、何度か遺言の内容を書き換えることが予想できる場合には、弁護士や司法書士など法律専門家の関与のもと、自筆証書遺言のリスクを最小限に抑えることが望ましいでしょう。
当事務所では、数多くの遺言書作成に携わっており、遺言書の文案作成、公証人役場との調整、遺言の執行など、遺言書に関する様々な手続きを取り扱っております。
遺言や相続についてお悩みの方は、当事務所までご相談ください。
遺言書の作成 ご依頼の手順
 ご予約
ご予約
当事務所まで電話またはメールフォームで、「遺言書作成のご依頼(ご相談)」をご希望の旨ご連絡ください。
日程調整のうえ、面談日時を決定いたします。
持参いただきたい書類等のご案内もさせていただきます。
 面談
面談
面談日時に当事務所までお越しください。 >アクセス
相続の内容や不動産の所有状況をお伺いした上で、手続きの方針を決定し、戸籍謄本などの必要書類や財産内容の確認から着手いたします。
 遺言書の文案作成・作成方法の決定
遺言書の文案作成・作成方法の決定
各財産を誰にどのように分配するかをお決めいただき、その内容に応じて遺言書の文案を作成いたします。
遺言の作成方式(公正証書遺言・自筆証書遺言など)もご事情にあわせて決定します。
 遺言書の作成
遺言書の作成
公正証書遺言を作成される場合には、公証役場との打ち合わせや必要書類の事前提出の後、公証役場へ出向いて公正証書遺言の作成を行います(公証人による出張も可能)。
証人(2名)については必要に応じて当事務所にてご用意できます。
自筆証書遺言については、当事務所立会いのもと、ご本人に自筆で記載のうえ捺印いただきます。
 完了
完了
遺言書をお渡しいたします。
遺言書作成の後も、遺言内容の変更などございましたらお気軽にご相談ください。
遺言書作成 手続費用(目安)
| 司法書士報酬 |
公正証書遺言 60,000円(税別)~ 自筆証書遺言 80,000円(税別)~ |
|---|
※ 公正証書遺言の場合には、公証役場所定の手数料が別途必要となります。